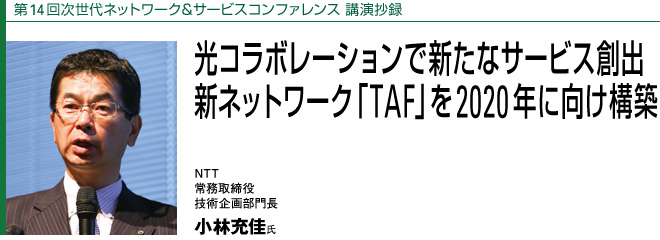日本は固定ブロードバンドの世帯普及率が49%、モバイルブロードバンドの人口普及率が119%と欧米諸国に比べて突出した状況にあります。一方、電子政府や電子カルテ、公務支援システムなど行政や医療、教育におけるICT利活用率は各国よりも低く、あまり進んでいません。ブロードバンド環境は整備されているにもかかわらず、改善の余地があるというのが実情です。
このインフラをいかに活用するかは大きな課題であり、NTTグループとしても新たなチャレンジとなっています。
その1つが、この5月にNTT東日本/西日本が発表した光サービス卸「光コラボレーションモデル」です。これまで「フレッツ光」ブランドで販売してきた光回線をいろいろな企業に大口割引料金で提供するもので、これらの企業は光回線を自社のサービスとパッケージにして自社ブランドで販売できます。フレッツ光は全国で1800万回線が使われていますが、近年、加入者の伸びが鈍化傾向にあります。光サービス卸は、その打開策として打ち出されたものです。
従来は光回線のアプリケーションをNTTグループが自ら考えて販売してきましたが、我々通信事業者の能力には限界があります。多様なパートナーの力を借りて、サービスをイノベートしていきたいと考えています。
こうしたコラボレーションモデルを伸ばしていくには、工事の進捗、課金、障害、回線品質などの情報をパートナー企業にリアルタイムで提供できる環境の整備が不可欠です。そのための基本技術がNFVやSDNであり、それらを包含する形でクラウド技術があります。これらをWANの世界で実現するには課題を克服し、競争力のあるコストを提供する必要があります。
このコンセプトをNTTでは「TAF(Trusted and Adaptive Fabric)」と呼んでいます。語呂合わせになりますが、パートナーのさまざまな要望に迅速かつ的確に対応する、信頼感としなやかさを併せ持った“タフな”ネットワークを作って行こうという思いが込められています。来年5月の決算発表でその具体策を明らかにする予定です。
TAFを夢物語に終わらせないために、グループ各社ではすでにいくつかの取り組みを進めています。
ドコモは今年10月、アルカテル・ルーセントやシスコシステムズなど世界の主要なベンダー6社の協力を得て、マルチベンダー環境におけるパケット交換機(EPC)へのネットワーク仮想化技術適用の実証実験に成功しました。2015年度にネットワーク仮想化技術のNFDの商用化を目指すとともに、将来的には適用範囲を音声交換機や位置情報管理装置などに広げていきます。
また、NTTコミュニケーションズが2013年に買収した米Virtela Technology Services Incorporated(バーテラ)は、WAN高速化やファイアウォールなどのCPE(顧客宅内装置)機能、SSL-VPNのセンタ装置機能をお客様のネットワーク側で仮想化し、カスタマコントロールできるというサービスを北米で提供しています。NTTコムはバーテラを傘下に置いたことで、日本向けにカスタマイズしたサービスを国内で展開する計画です。
仮想化については、こうしたところから一歩一歩進めていきます。
最近、ビッグデータという言葉がしばしば使われますが、通信では日々、数億〜数十億ものデータが発生しています。NTTの研究所が持つデータ集積技術や分析技術を使い、サイバー攻撃やトラフィック変動、装置故障などの予兆を検知し、回避する「プロアクティブ制御」により、通信事業者のオペレーションコストも削減できると見ています。
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、世界に先駆けてTAFを実現すべく積極果敢に挑戦していきたいと考えています。
(文責・編集部)