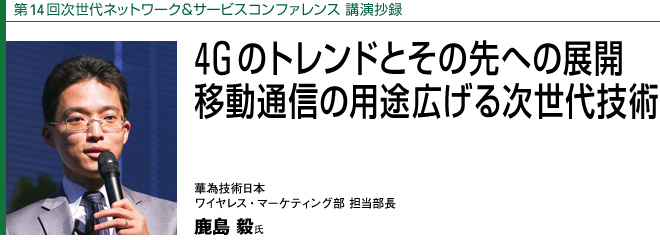世界市場で急速に普及が進んでいるLTE/LTE-Advanced(4G)のトレンドと私どものソリューションに触れた上で、4Gの拡張技術と5Gに向けた当社の取り組みについて話をして参ります。
日本の携帯電話市場は、料金や端末商品力の競争を経て、「ユーザー体験」──利用者が体感する通信速度をインフラの拡充で競う段階に入っています。ユーザー体験の向上には、ピーク速度だけでなく平均速度やセルエッジ速度も向上させ、快適な通信ができることが重要だと考えています。
これを実現する有力な手段の1つにキャリアアグリゲーション(CA)がありますが、当社は今年、FDD LTEにおいて搬送波を3CC(Component Carrier)で450Mbps、TDD LTEにおいて4CCで1Gbps以上の速度を実現するシステムのデモを行いました。MIMOなどのマルチアンテナ技術も体感速度向上の有力な手段です。
体感速度向上を図る上で重要なのが新たな周波数帯の追加です。他方、携帯電話で利用される周波数帯が多くなると、基地局の設備も増えてきますが、基地局が設置できるスペースは限られています。そこで当社ではアンテナと無線機を一体化したアクティブアンテナシステムの開発など、機器の集約化に注力しています。Software Defined Bandという技術を使って世界で初めて1台の無線機で365MHz幅という非常に広い帯域をカバーし、1.8GHz帯と2.1GHz帯といった複数のバンドをサポートできるようにしました。2018年にはカバー帯域を最大800MHzに拡大する予定です。
基地局の高密度化も有力な手段ですが、設置場所の確保が大きな課題となっています。そこで当社では街灯などに容易に設置できる小型のアンテナ一体型マクロ基地局を開発しました。LampSiteというソリューションはイーサネットを使って多数の小型屋内基地局を容易に整備できるもので、北京国際空港ではこれを用いて2200以上の基地局が設置されました。
セルエッジのスループットの改善には、多数の基地局のベースバンドユニットを1カ所に集約し協調を容易にするCloudBBが有力な解決策になると考えられます。当社はこれらのソリューションを通じて携帯電話事業者のユーザー体験向上に貢献してまいります。
さて、今後モバイルネットワークには、(1)IoT、M2Mで想定される非常に多くのデバイスの接続への対応、(2)自動運転やVirtual Reality、e-Healthなどのクリティカルな用途に対応できる低遅延化、(3)4K、8K時代に向けた高速・大容量化が求められることになると考えられます。来年から2020年の5年間は、これらの実現に向け、LTEのさら更なる拡張とその次の5Gの研究開発を進めていく期間になります。
LTEの拡張では、(a)携帯電話の主要なバンドをすべてCAで束ねて使えるようにする技術や、(b)アンライセンスバンドをライセンスバンドと一体的に運用する技術、(c)Massiveアンテナを使った3GビームフォーミングやマルチユーザーMIMO、(d)256QAMの導入などが想定されています。また(e)10年以上電池の交換なしで使え、より広いカバレッジを持つナローバンドM2Mの実用化も期待されています。
その先の5Gでは更なる機能改善によって用途が格段に広がります。5Gでは、用途に応じて複数の通信規格を作るという考え方もあるようですが、当社は多様な用途にリーチでき、あらゆる周波数帯で利用可能な1つの新しい通信規格を作りたいと考えています。
標準化はまだこれからですが、世界のキャリア、ベンダーと協力して5Gを作り上げていきたいと考えています。当社では昨年5Gの研究開発に2018年までに6億ドル(600億円強)を投資すると発表、ミリ波帯でのリアルタイム115Gbps伝送装置のプロトタイプを世界で初めて実現するなど、新技術の開発に積極的に取り組んでおります。
(文責・編集部)