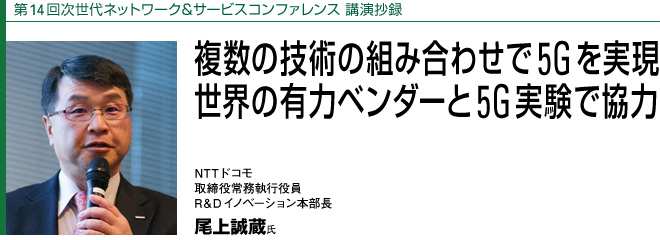これまでのセルラー技術の歴史を振り返ると、PDCやGSMなどデジタル携帯電話(2G)のTDMA、3GのW-CDMA、LTE/LTE-Advanced(4G)のOFDMAなど、10年ごとに新しい世代の技術が生まれ、20年たってその技術がピークを迎えています。ただ、これは世界全体の話であり、日本ではその技術を活用したシステムが20年後には終わっています。日本をはじめとする先進市場が新たな技術を生み出し、それが世界中に浸透するということを繰り返してきたといえます。
これに対し、2020年頃に実用化が見込まれる5Gは標準化に向けた議論が行われている段階で技術仕様が固まっていないこともありますが、まだ中身がなく代表的な技術が存在しません。しかし、複数の技術の組み合わせによって新しいフィーチャーを作り出すことはできる、と1年ほど前からは考えるようになりました。
技術の組み合わせの具体例として、LTE-Advancedではキャリアアグリゲーション(CA)やスモールセルなどにより、高速かつ大容量を実現します。いずれも既存の技術で新しいアイデアはありませんが、組み合わせによって良い特徴が生まれるのです。同様に、5Gも技術の組み合わせで十分可能なのではないかと思っています。
その5Gは、超高速で超大容量キャパシティを提供するため、「非常に広い周波数帯域幅を使う」「非常に高い周波数スペクトラムを使う」「伝搬損失が大きい」「電波が届かずカバレッジが狭い」といったことを根拠に、ホットスポット的に補完するもの、という見方があります。
これは私が嫌いな、「間違ったストーリー」です。すなわち、非常に高い周波数を使ってもセルラーシステムの進化としてのカバレッジを実現する技術に挑戦しようと訴えています。
そのための技術として着目しているのが「Massive MIMO」で、基地局に100以上のアンテナ素子を設置して高速化を図るものです。ところが、単にアンテナ数を増やすだけでは力業にすぎません。そこで、高度化C-RANによるアドオンセルの展開を考えています。CAによりマクロセル用周波数帯とスモールセル用周波数帯を1つにまとめるというコンセプトです。これにより、マクロセル内のスモールセルのエリアに入っても端末にとっては同じセルの中にいるのと同じ状態になり、ハンドオーバー処理が発生しなくなります。要するに、最低限のコネクティビティはマイクロセルで担保しつつ、容量の拡大はスモールセルで確保するわけです。ドコモではこのCAを来年早々にも導入する予定です。
ところで、世界における5Gに関する活動を見てみると、ITUや3GPP、GSMAといった国際的な機関でも技術仕様などの検討を始めています。特筆すべきは、日本で産学官連携による「第5世代推進フォーラム(5GMF:The Fifth Generation Mobile Communications Promotion Forum)」が発足したことです。
5Gのコンセプトについては、4Gの発展系となるシステムと新たな無線システムを組み合わせたものになると見ています。10Gbps超のスループットや1000倍のネットワーク容量、1m秒以下のネットワーク遅延といった高い要求条件を満たすことで、従来の移動通信システムでは対応できなかったさまざまな利用形態をカバーできるようになります。
これまで、ドコモでは新しい世代のサービスを開始した直後に次の世代の研究に着手してきました。5Gについても2012年から始めており、リアルタイムシミュレーションを開発しているほか、世界の主要ベンダーと5Gに関する実験で協力しています。2020年には、さまざまなユースケースをカバーし、多くの周波数を効率よく使えるサービスを実現したいと考えています。
(文責・編集部)