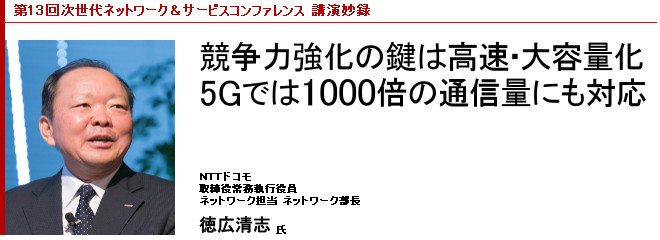ドコモが進めるLTEネットワーク強化策の柱は、①1.7GHz/1.5GHz帯を活用した100Mbps超の高速データ通信、②2.1GHz/800MHz帯を活用した全国エリアの早期構築、③4つの周波数帯を活用した大容量インフラの整備の3つ。2015年以降のLTE-Advancedの導入でさらなる高速・大容量化を実現。20年以降の実用化が見込まれる5Gでは1000倍の通信量への対応を目指す。
iPhoneの導入以降、よく「ドコモは他社に押され気味だが、どう巻き返していくのか」と聞かれるようになりました。
今日はネットワーク担当の立場からこの質問にお答えすると同時に、2015年以降に導入予定のLTE-Advanced、その次の5Gについても触れていきたいと思います。
スマートフォンの登場を機に、携帯電話のデータトラフィックは非常に大きな伸びを見せるようになりました。現在のペースが続けば、5年後に10倍、10年で100倍、15年後には1000倍になってしまう。これに対応できる大容量のネットワークを作っていくのが、私どもの大きなミッションです。
その手段の1つとして携帯電話事業者は、3Gのネットワークをより快適な高速通信ができて、周波数利用効率も高いLTEに変えていこうとしています。
ドコモは2009年から、3Gの主力バンドとして使ってきた2.1GHz帯の20MHz幅の帯域の中で3G(W-CDMA)1波分にあたる5MHz幅、4車線の道路でいえば1車線をLTE用に変えて、下り最大37.5Mbpsの高速データ通信サービスを提供してきました。昨年秋からはLTEのレーンを順次2車線(10MHz幅)に拡げ、最大通信速度を75Mbpsに向上させています。これによりLTEのお客様の増加でやや速度が出難くなっていた都心でも快適にお使いいただけるようになっています。
ところが、iPhone 5s/5cの発売に合わせて、ライバル会社がこうしたLTEの2車線化を複数の周波数帯で実施したため、当社のサービスはやや見劣りするようになってしまいました。
そこで、ドコモはiPhone 5s/5cが発売された9月20日から関東の一部の基地局を1.7GHz帯の4車線分(20MHz幅)を一気にLTEに切り替えて運用するようにしました。東京、名古屋、大阪の都心ではすでに4車線対応のLTE基地局を使って、iPhoneでは下り最大100Mbps、10月に販売を開始したAndroidスマートフォンでは国内最速の下り150Mbpsでのデータ通信を可能にしました。他社がトラフィック対策に苦しんでいる都心で圧倒的な通信速度を実現することで、巻き返しが図れると考えています。13年度末には150Mbps対応基地局を500局に、14年末に2000局にする計画ですが、前倒しも検討しています。
1.7GHz帯の割当は東名阪地区限定なのですが、それ以外の地区でも昨年末から1.5GHz帯を使って下り112.5Mbpsのサービスを開始、すでに全都道府県で100Mbpsを超えるサービスが利用できるようになっています。
エリア面でも6万カ所ある800MHz帯/2.1GHz帯3G基地局へのLTEの導入を急ピッチで進めています。さらに1.7/1.5GHz帯の利用開始で都心部では2倍に増えた周波数資源を有効に活用、どこでも快適につながるネットワークを実現していきます。
「速く」「広く」「快適な」ネットワークを最適なバランスで構築してお客様にご満足いただく――これがドコモの巻き返し策の全体像です。
さらにドコモでは、2015年度以降にLTEの発展系となる4G(第4世代移動通信システム)LTE-Advancedを導入、①LTEキャリアを束ねて同時送信し伝送速度を向上させる「キャリアアグリゲーション」、②通常の大セル基地局のエリア内に小型の張り出し装置を配置し、大セル基地局と連携して無線を拡大する「アドオンセル」などの技術を活用し、さらなる高速・大容量化を実現していきます。
加えて2020年頃の実用化が見込まれている5G(第5世代移動通信システム、FRA:Future Radio Access)に向けた議論にも積極的に取り組んでいます。5Gでは現行システムの100倍の超高速通信、1000倍の超大容量化がターゲットとなります。ドコモでは15年後の1000倍のトラフィックへ対応をにらみFRAの研究開発にも注力して参ります。
(文責・編集部)